 ぴよきち
ぴよきちこんにちは!
今回は、寝たきりになる原因とその理由についてお話ししたいと思います。
寝たきりとは、長期間にわたって一日の大半をベッドの上で過ごし起き上がれない状態のことです。
寝たきりになると、身体的にも精神的にも苦しみが増えるだけでなく、介護費用や医療費用もかさみます。
寝たきりにならないためには、日頃から適度な運動や社会的な活動、バランスの良い食事などを心がけることが大切です。
また、病気やケガの予防や早期発見・治療も重要です。
今回、寝たきりの原因となる代表的なものを10個挙げてみました。順位は10位から始めて、1位に近づくにつれて寝たきりになるリスクが高くなるものとします。
10位:褥瘡
褥瘡とは、床ずれのことで、皮膚が圧迫されて血の巡りが悪くなり、赤みや水ぶくれ、内出血などが見られる状態です。
寝たきりの人は、同じ姿勢で長時間圧力がかかることで褥瘡を起こしやすくなります。
褥瘡は痛みや感染のリスクを伴い、治癒に時間がかかります。
褥瘡を予防するためには、定期的に体位を変えたり、保湿や清潔に気を付けたりすることが必要です。
また、褥瘡ができた場合は、早めに医師に相談し、適切な処置を受けることが大切です。
9位:うつ状態
うつ状態とは、気分が落ち込み、やる気や興味がなくなる状態です。
高齢者は孤独感や生きがいの喪失、病気やケガなどのストレスなどでうつ状態になりやすくなります。
うつ状態になると、食欲や睡眠が乱れたり、自殺念慮が生じたりすることがあります。
うつ状態を改善するためには、心理的なサポートや適切な薬物療法、趣味や交流などの活動を行うことが効果的です。
また、うつ状態が続く場合は、専門の医師やカウンセラーに相談することも必要です。
8位:起立性低血圧
起立性低血圧とは、急に立ち上がったりした時に、血圧が下がり立ちくらみやめまいなどを起こす状態です。
高齢者は自律神経の働きが低下し、血圧の調節がうまくできなくなることで起立性低血圧を起こしやすくなります。
起立性低血圧は、転倒や失神などの危険を伴い、外出や運動が億劫になります。
起立性低血圧を防ぐためには、ゆっくりと起き上がることや、水分や塩分の摂取、着圧ソックスなどの着用などが有効です。
また、起立性低血圧の原因となる薬剤や疾患がある場合は、医師に相談することも必要です。
7位:心機能の低下
心機能の低下とは、心臓の働きが悪く、全身に十分な血液を送り出せない状態です。
高齢者は心筋が硬くなったり、心臓弁が狭くなったりすることで心機能が低下しやすくなります。
心機能の低下は、動悸や息切れ、むくみなどの症状を引き起こし、活動性を低下させます。
心機能の低下を改善するためには、適度な運動や塩分の制限、血圧や血糖のコントロール、薬物療法などが必要です。
また、心不全や心筋梗塞などの重篤な病気の予防や早期発見・治療も重要です。
6位:誤嚥性肺炎
誤嚥性肺炎とは、食べ物や唾液などが誤って気管支や肺に入って起きる肺炎です。
高齢者は嚥下機能が低下し、誤嚥性肺炎を起こしやすくなります。
誤嚥性肺炎は重症化しやすく、呼吸不全や敗血症などの合併症を引き起こすことがあります。
誤嚥性肺炎を予防するためには、食事の形態や量、食べ方、口腔ケアなどに注意することが大切です。
また、誤嚥性肺炎が疑われる場合は、早めに医師に相談し、抗生物質などの治療を受けることが必要です。
5位:廃用症候群
廃用症候群とは、長期間の安静状態や運動量の減少によって身体機能が衰え、心身の様々な機能が低下することです。
廃用症候群になると、筋力や骨量、内臓機能、精神機能などが悪化し、寝たきりになる可能性が高くなります。
廃用症候群を回復するためには、日常生活動作や運動療法、栄養補給などを行うことが必要です。
また、廃用症候群の原因となる疾患や薬剤の見直しも重要です。
4位:骨折・転倒
骨折・転倒とは、高齢者が骨粗しょう症などで骨が弱くなり、転んだり足を踏み外すだけでも骨折することです。
特に大腿骨頸部の骨折は多く見られ、手術やリハビリに時間がかかり、歩けなくなるリスクがあります。
骨折・転倒を予防するためには、骨密度の測定やカルシウムやビタミンDの摂取、転倒防止のための環境整備やバランス感覚のトレーニングなどが有効です。
また、骨折が起きた場合は、早めに医師に相談し、適切な治療やリハビリを受けることが必要です。
3位:高齢による衰弱
高齢による衰弱とは、加齢によって筋力や関節、臓器などの身体機能が低下し、活動性が減少する状態です。
高齢による衰弱が進むと、体を動かすことが億劫になり、寝たきりになりやすくなります。
高齢による衰弱を防ぐためには、日常生活動作や運動療法、栄養補給などを行うことが必要です。
また、高齢による衰弱の原因となる疾患や薬剤の見直しも重要です。
2位:脳卒中
脳卒中とは、脳の血管が詰まるか破れることで、脳に血液が行き届かなくなり、脳の神経細胞が障害される病気の総称です。
脳卒中によって、麻痺や失語などの後遺症が残り、思うように動けなくなることがあります。
脳卒中を予防するためには、血圧や血糖、コレステロールなどの管理、喫煙や飲酒の控えめ、ストレスの軽減などが有効です。
また、脳卒中の早期発見・治療のためには、自分の体の変化に気を付けることや、救急車を早めに呼ぶことが必要です。
1位:認知症
認知症とは、脳の神経細胞が障害されて認知機能が低下し、日常生活に支障が出る状態です。
認知症が進行すると、自力で起立や歩行、排泄などができなくなり、寝たきりになるリスクが高まります。
認知症を予防するためには、脳トレや社会参加、適度な運動や食事、睡眠などの生活習慣の改善などが効果的です。
また、認知症の早期発見・治療のためには、自分の記憶や判断力に問題がないかチェックすることや、医師や専門機関に相談することが必要です。
まとめ
以上が、寝たきりになる原因10選とその理由についてでした。
寝たきりになる原因はさまざまですが、代表的なものとして、認知症、脳卒中、高齢による衰弱、骨折・転倒、廃用症候群、誤嚥性肺炎、心機能の低下、起立性低血圧、うつ状態、褥瘡などが挙げられます。
これらの原因は、それぞれに対応した予防や治療が必要ですが、共通して言えることは、日頃から適度な運動や社会的な活動、バランスの良い食事などを心がけることが大切だということです。
また、病気やケガの予防や早期発見・治療のために、自分の体の変化に気を付けることや、医師や専門機関に相談することも必要です。
寝たきりになると、身体的にも精神的にも苦しみが増えるだけでなく、介護費用や医療費用もかさみます。
寝たきりにならないように、健康に気を付けてくださいね。
この記事が、寝たきりに関心のある方や、寝たきりになりたくない方にとって、参考になれば幸いです。
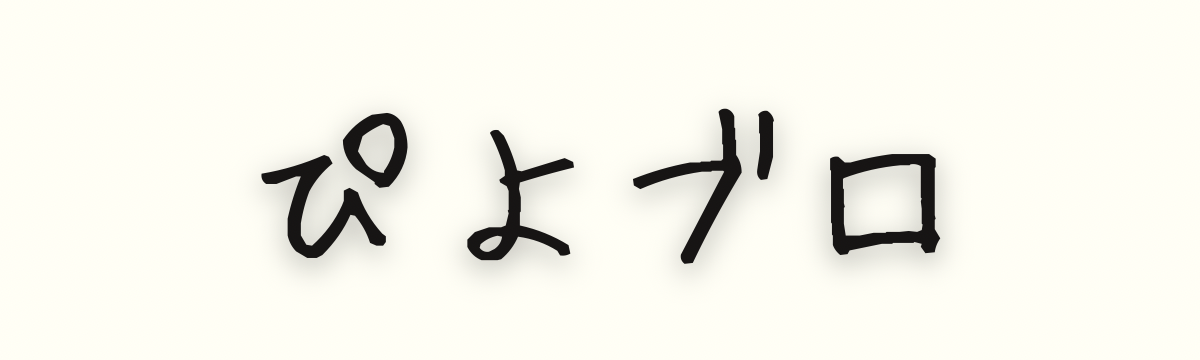
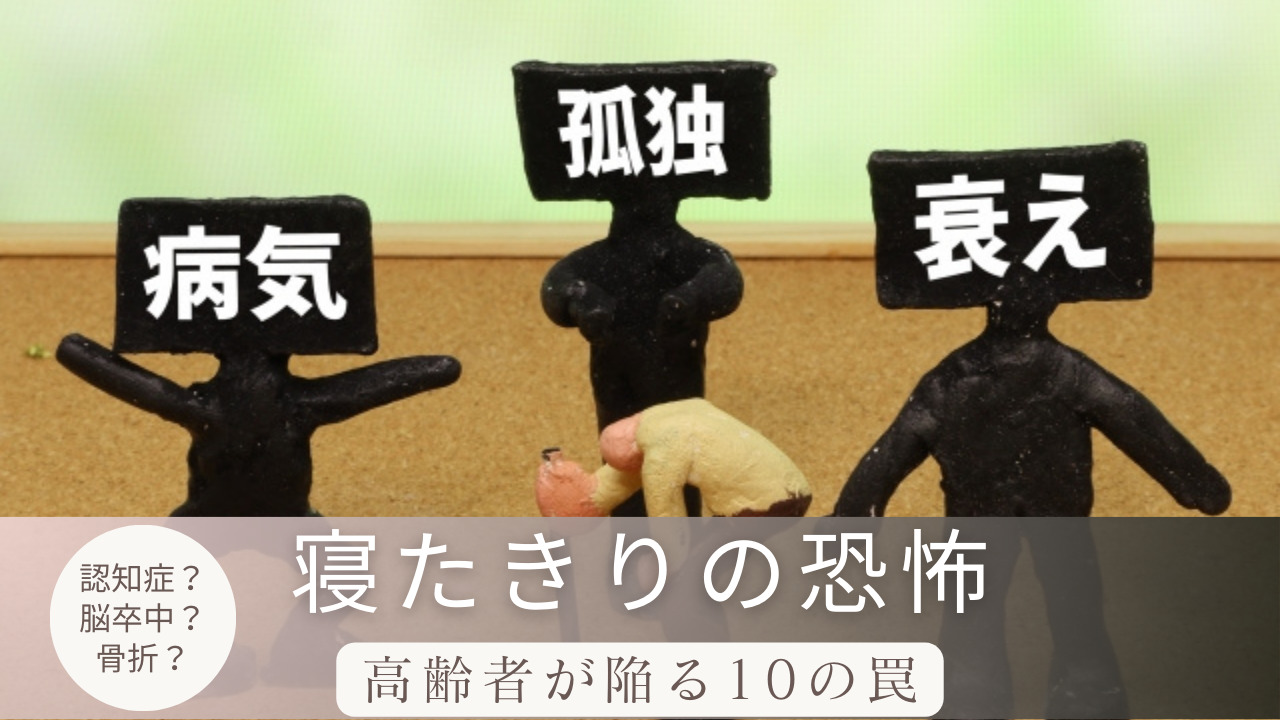

コメント